論文タイトル
Dynamics and non-canonical aspects of JAK/STAT signalling
出典
Eur J Cell Biol. Jun-Jul 2012;91(6-7):524-32.

読んだ動機
STATがリガンド応答性の人工転写因子として活用できるか検討するため、STATのリン酸化がどのように自身の活性化を促しているか確認したいと思っています。そもそも一般的なJAK-STATシグナルとは異なるSTATの活性化メカニズムも知られているため、それについての総説の内容を確認しました。
要旨
non-canonical JAK-STATシグナルのメカニズムの解説しているレビュー論文です。
章立て
- イントロダクション
- canonical/non-canonicalそれぞれのシグナル伝達メカニズム概要
- サイトカイン受容体の活性化
- gp130について
- STATの2量化と活性化
- STATの核移行
- STATの非古典的(non-canonical)な機能
感想
この場では古典的な]AK-STATのシグナル伝達メカニズムの解説は割愛します(本論文のIntroductionに記載されています)。
まずnon-canonicalなSTATのシグナル伝達メカニズムでは、非リン酸化状態においても一部のSTATが2量化されていることが前提となっています。リン酸化によりこのSTAT2量体の立体構造が変化することで、はじめて活性化されるとのことです。
非リン酸化状態におけるSTATの2量体化には、STATのN末端ドメインが重要な役割を担っています。しかしその寄与度はSTATの種類(STAT1,STAT3など)により異なるとのことです。例えばSTAT3のN末沿ドメインは活性化にわずかにしか影響しないことが知られています。
さらにSTAT3のLys685のアセチル化は2量体の形成を安定化しているようです。
核移行についても同様で、非リン酸化状態においても一定数STATは核内に存在し、核内外の遷移が平衡に達する結果として、定常的な核内存在量が規定されます。STATのリン酸化は、この平衡を核内蓄積に向けてシフトする役割を果たします。
STATの核移行には、exportinやimportinが関与しています。またSTATと核膜複合体と直接相互作用することで核内に移行されるメカニズムも存在するとのことです。
この総説内では、こういう裏づけデータがあるという事実の羅列に終始している印象でした。強固で画ー的な理論が提唱されていないこと、さらにSTATの種類によってもメカニズムが若干異なることがその主な理由でしょう。STATを対象としてエンジニアリングする場合には、複雑な仕組みの中で、支配的なメカニズムにフォーカスする必要がありそうです。
次に読みたい論文
STATのnon-canonicalシグナルを理解するにあたって、exportin/importin、核膜複合体、シグナル伝達エンドソーム、徴小管形成(stathimin)に関する基本的な分子メカニズムを埋解する必要があると感じました。



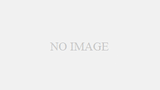
コメント