論文タイトル
Reprogramming cell fate with artificial transcription factors
出典
FEBS Lett. 2018 Mar;592(6):888-900.

読んだ動機
これまで受容体によるセンシング技術の方向から、リガンド応答性の遺伝子制御システムについて考察してきました。今回は、転写因子のエンジニアリングという方向から、できることがないか考えていきたいと思います。これまで報告された、人工転写因子のデザインに関する総説があったので紹介していきます。
要旨
過去に報告された主要な人工転写因子(ATF)のデザインについてレビューする総説です。
章立て
- イントロダクション
- ATFのプラットフォーム
- CRISPR-Cas
- TALES
- 化学合成(非天然修飾)によるATF
- Zinc fingers (ZF)
- 細胞の運命制御へのATF応用
- 複数のATFを組み合わせる
- ZF-ATFライブラリと実験手法
- 遺伝子発現制御における可塑性
- 将来展望
- 結言
感想
一般的な人工転写因子のデザインは、(1)DNA結合ドメイン(DBD)、(2)相互作用ドメイン(ID)、(3)エフェクター(転写活性化)ドメイン(ED)の3つからなります。
IDは、内因性で存在する他の転写制御因子が結合する足場を提供し、EDと合わせてより強固に転写活性を制御するためのドメインです。
著者はZFベースのATFを研究しているため、CRISPR-CasやTALEの技術課題を示したあと、ZF-ATFの動作原理や活用事例を紹介する流れで議論が展開されています。
CRISPR-CasやTALEは標的にDNAに対する特異性を高く設計できる反面、10ヌクレオチド以上の長いDNA鎖を認識するため、染色体上の複数の領域を標的とすることは難しい技術です。またCRISPR-Casは分子サイズが大きいため効率的な細胞への送達を困難にします。
ZFは一つのDBDで3コドン(9ヌクレオチド)を認識し、一般にはそれを3つなどタンデムで使用することで、より長い領域を標的とします。ZFの認識はVNNなど縮重塩基(VはA/C/G、NはA/C/G/T)を許容するように設計することができるため、標的配列の広範性と特異性のバランスをとることが可能です。
実際にOct4の代替となるZF-ATFのスクリーニング事例が紹介されていましたが、取得された11種類のATFsは、それぞれ異なる遺伝子を活性化しており、異なる経路で同じ目的の表現型を達成していることが示されていました。
次に読みたい論文
本論文内では、リガンド応答性のATFについては言及がありませんでした。引き続きATFに細胞外リガンドの応答性が付与できるか検討するため、天然の転写因子の活性化メカニズムについても確認していきたいと思います。


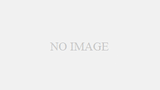
コメント