論文タイトル
Tracking STAT nuclear traffic
出典
Nat Rev Immunol. 2006 Aug;6(8):602-12.
確認したいこと
- STATの核移行メカニズム
要旨
一般的なタンパク質の核移行メカニズムと、STATs(主にSTAT1、STAT2、STAT3)についての核移行に関する知見がレビューされています。
章立て
- イントロダクション
- STATファミリーについて
- STATの生物学的な役割
- タンパク質の核輸送メカニズム
- 核移行に関連するシグナル配列とトランスポーター
- STAT1の核輸送(核輸送とDNA結合との関連性について)
- STAT1の核内輸送
- STAT1の核外輸送
- STAT2の核輸送(STAT2の2面性)
- リン酸化STAT2とSTAT1のヘテロ2量体における核内輸送
- 非リン酸化STAT2のIRF9依存的な核内輸送
- STAT2の核外輸送
- STAT3の核輸送(リン酸化非依存的な輸送について)
- STAT3の核内輸送
- STAT3の核外輸送
- STAT5の輸送(類縁STATからの考察)
- 非哺乳類のSTATにおける細胞内局在
- 結言
考察など
基礎的な核移行の分子メカニズムも詳しく解説されていて、とても参考になりました。
そもそも、核内移行シグナル(NLS)・核外移行シグナル(NES)は、それぞれ importin、exportin と呼ばれる、細胞内タンパク質に対する結合サイトとして機能します。
importin、exportin は核膜孔複合体を形成するヌクレオポリンと相互作用することで、効率的な核輸送を補助しています。importinが輸送体、NLSをもつタンパクがその積み荷となるイメージです。
核輸送の方向性は、RAN-GTP濃度で制御されています。具体的には、核内の方が細胞質よりRAN-GTPの濃度が高いため、RNA-GTPとimportinは、核内で結合できるようになります。それによって、積み荷分子を降ろすことができるようになるそうです。
4章から、STATに焦点を当てた話題になります。
まずSTAT1においては、リン酸化に伴う構造変化によって、importinが結合するためのLeu407が露出します。これによって核に移行できるようになります。
ここから話が複雑になってきます。
まずSTAT1は、既知のNLSとは別にimportinに結合できるサイトがあり、その相互作用もまた核移行に大きく寄与するそうです。
また、STAT2やSTAT3はリン酸化非依存的に核移行できる機構があります。例えばSTAT3は、importin α3によって恒常的に核移行するとのことです。
論文を読んで、核輸送の分子メカニズムは想像より単純に思いました。リン酸化することで、importinに結合できるタンパクモジュールがあれば、核輸送をシグナルで制御できるのかも。
追加調査したいこと
- 各importinファミリーの核輸送への寄与(支配的なimportin種を同定したい)
- DNAとSTATのDNA結合ドメインとの結合様式(またSTATのDBDをエンジニアリングして、転写遺伝子の特異性を変えることができるか)



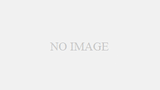
コメント