論文タイトル
Importin α : functions as a nuclear transport factor and beyond
出典
Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2018;94(7):259-274.
確認したいこと
- importinの核輸送メカニズム
リン酸化修飾によって機能する、NLSをデザインしたいと思っています。
要旨
タンパク質全般の核輸送メカニズムから、importin αの生理的な役割について詳述されたレビュー論文です。
章立て
- イントロダクション
- 核局在化シグナル
- 核輸送関連分子の発見
- 核輸送分子機構
- 核膜孔複合体
- 核輸送受容体
- importin α
- importin β
- Ran GTPase
- 古典的な核移行の分子メカニズム
- importin αの研究からわかったこと
- importin αの主要機能
- 哺乳類のimportin αにおける各サブタイプの生理学的意義
- importin αの予期せぬ機能
- 細胞質における機能
- importin βに対するアダプタータンパク以外の役割
- プロテアソームとの連携
- 紡錘体の形成
- ニューロンにおける逆行軸索輸送
- ストレス性顆粒
- 核内における機能
- 核膜孔における機能
- 核膜とラミン集合と核収縮
- 細胞膜における機能
- 膜型のimportin α
- 細胞質における機能
- 結言
考察など
importinとNLSに関する内容を中心に、理解を進めていきました。
まず、NLSは一般的に塩基性アミノ酸を中心に構成されています。これを古典的NLS(cNLS)と呼びます。
cNLSには、単一の塩基性クラスタをもつ単部型(monopartite)(例:SV40, PKKKRKV)と、2つの塩基性クラスタをもつ二部型(bipartite)(例:ヌクレオブラスミン、KRPAATKKGQAKKKK)の2種類が存在します。
一方、importin αはNLSを合むタンパク質とimportin βと3者複合体を形成して、核膜孔を通過します。
importin βは、核膜孔複合体と直接相互作用して、核内への効率的な移行に貢献します。
importinα は、importin β結合ドメイン(IBB)、cNLS結合ドメインであるアルマジロ(Arm)リピート、importin αの核外輸送に関わるCAS/CSE1Lに結合するC末端ドメイン、の3つで構成されます。
Armリピートは、10個の反復配列からなるドメインです。10個のうち、2-4個目の領域が主要NLS結合部位(major site)、6-8個目が補助的な結合部位(minor site)といわれています。NLSは主に「major site」に結合し、二部型のNLSは、その片側が「minor site」にも結合します。
また、importin αは、核膜孔複合体を構成するNup153と結合することで、核移行を補助することもできます。
タンパクのエンジニアリングにおいて、どうしてNLSが、importin αのIBBより使用されるのでしょうか。
私見ですが、ひとつには、NLSが比較的短いモチーフであるからだと思います。ちなみに、IBBは60残基程度の配列です。
ふたつめは、importin α自身も、核膜孔複合体と相互作用することで、核膜の通過に直接貢献する点です。これがどれくらいの寄与かわかりませんが、十分な核輸送にはimportin αが必須かもしれません。
タンパクによっては、cNLSを持たず、importinβ と直接結合することで核移行するタンパクもあります。求める活性レベルにより必要性の有無は変わるのでしょうか。
もちろん歴史的な経緯、使用実績がcNLSを利用する主要な理由であると思いますが、上記の点についても、頭の片隅に置いておきたいです。
追加調査したいこと
- cNLSの配列多様性やコンセンサス配列
- importin αサブタイプとArmリピートの多様性
- cNLSとimportin αの複合体構造



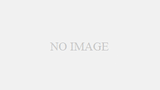

コメント