論文タイトル
Programmable base editing of A・T to G・C in genomic DNA without DNA cleavage
出典
Nature. 2017 Nov 23;551(7681):464-471.

Programmable base editing of A•T to G•C in genomic DNA without DNA cleavage - PubMed
The spontaneous deamination of cytosine is a major source of transitions from C•G to T•A base pairs, which account for half of known pathogenic point mutations ...
確認したいこと
AID (シチジンデアミナーゼ) 以外の塩基編集技術
要旨
部位特異的なA・T → G・C 変異を導入するために、CRISPR-Cas9にアデノシンデアミナーゼを融合したタンパク質を創生した、という論文です。
用語
- ABE: adenine base editor
- ecTadA: Escherichia coli TadA
- TadA*: TadA variant
- XTEN: 16 amino acid linker
- AAG: Alkyl adenine DNA glycosylase
解説など
シチジンを編集するシチジンデアミナーゼをCRISPR-Casに融合する技術はありましたが、これまでA・T→G・C 変異を効率的に導入できる技術は存在していませんでした。
ABEは、TadA*/TadA-XTEN-nCas-NLS (=ABE7.10, 後述) という融合タンパク質として、デザインされています。
各コンポーネントの役割は以下のとおりです。
- TadA*/TadA: TadAは、大腸菌由来のアデノシンデアミナーゼです。またTadA*はTadAの活性を向上させた改変体です。野生型のTadAと2量体を形成して活性を有するため、タンデムに連結されています。
- XTEN: 16アミノ酸で構成されるリンカー
- nCas: ニッカーゼ活性を有するCRISPR-Cas9変異体
- NLS: 核移行シグナル
この論文の驚くべきは、最適なABEを探索するために、7回もの分子進化実験を行っている点です。大腸菌内で抗生物質耐性遺伝子に終始コドンを挿入し、TadAが活性を示すときに、遺伝子機能が回復することを指標として、改変体を選抜しています。
野生型のTadAから以下の変遷を経て、改変体が構築されています。
- ABE0.1 (wtTadA-Cas9 nickase)
- ABE1.1 (ABE0.1 + D108N)
- ABE1.2 (ABE1.1 + A106V)
- ABE2.1 (ABE1.2 + D147Y + E155V)
- ABE2.9 (ABE2.1, homodimer)
- ABE3.1 (ABE2.9 + L84F + H123Y + I156F)
- ABE5.1 (ABE3.1 + H36L + R51L + S146C + K157N)
- ABE5.3 (ABE5.1, heterodimer)
- ABE6.3 (ABE5.3 + P48S)
- ABE7.10 (ABE6.3 + W23R + S48A + R152P)
これらの技術は最終的に、各塩基を対象としたエディターが最適化されたのちに、組み合わされて使用するという方向性が、あり得るのではないかと思います。均質な変異導入を実現できるツールとなると良いと感じました。




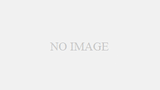
コメント