論文タイトル
Protein three-dimensional structures at the origin of life
出典
Interface Focus. 2019 Dec 6;9(6):20190057.

確認したいこと
タンパク質の構造を形作る、モチーフの役割について調べてみました。
要旨
生命の古い起源から活用されたと考えられる、4種類のアミノ酸モチーフについて解説されています。
章立て
- 緒言
- ネスト
- カリウムチャネル
- アミロイド/αシート
- 金属配位ペプチド
- 進化初期のペプチド
解説など
タンパク質は核酸に比べて合成が容易なため、DNAやRNAの出現より前に、タンパク質の世界があった可能性が高いと、筆者らは主張しています。そのような古い時代から存在する、およそ8残基程度のペプチドモチーフの役割について解説された論文です。
1つ目は、ネストと呼ばれるモチーフです。代表的なネストにはPループがあります。PループはATPまたはGTPに結合するモチーフです。ATPやGTPなどの対象となる原子が、Pループの第1および第3ペプチド主鎖のNHと水素結合を形成することが特徴です。ループによる凹みにターゲットの原子が補足されるイメージです。そのほか、セリンプロテアーゼにみられるオキシアニオンホールや、フェレドキシンのような鉄-硫黄中心をもつ構造が、ネストに属します。
2つ目は、カリウムチャネルです。ネストが凹み部位を持つのとは対照的に、線状の構造が保持されたペプチドです。チャネルタンパク質においては、この構造が同心円状に集合することで、チャネルの孔を形成することができます。
3つ目は、αシートです。アルツハイマー病に代表されるアミロイドは、この構造を持つことが知られています。αシートの端には正電荷が局在し、もう一方の端には負電荷が局在するのが特徴です。この正電荷側が、細胞膜と相互作用することで、膜損傷を引き起こす可能性があります。
4つ目は、金属ペプチドです。キラリティのない平らな構造をもち、中心にNi、Cu、Feなどが配位します。
一般的にペプチド単体では、柔軟性が高く、安定した構造をもたないため、サイズの大きいタンパク質として存在することで、安定な構造とそれに伴う機能を発揮できるようになります。従って、タンパク質の中に存在するモチーフの役割を解析することが、大事なのかもしれません。



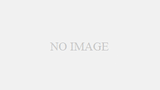
コメント