論文タイトル
Protein building blocks preserved by recombination
出典
Nat Struct Biol. 2002 Jul;9(7):553-8.

Protein building blocks preserved by recombination - PubMed
Borrowing concepts from the schema theory of genetic algorithms, we have developed a computational algorithm to identify the fragments of proteins, or schemas, ...
確認したいこと
タンパク質のフラグメント定義として紹介された、スキーマの原著論文を確認しました。
要旨
タンパク質の3次構造として再構築可能な1種のフラグメントとして、スキーマ(SCHEMA)の概念を紹介した論文です。
解説など
スキーマのアルゴリズムでは、遺伝子組み換えが起こり得る単位として、フラグメントが定義されていることが特徴です。
原理の概要は単純で、まず各アミノ酸残基が形成する相互作用を洗い出します。そのタンパク質が特定の箇所でフラグメント化されたときに、破壊される相互作用をスキーマプロフィール(S)として計算します。このSを最小化するフラグメントは、タンパク質内部の相互作用を最大数維持しますので、環境に有利であると考えられます。
本手法をタンパク質に適用すると、以下のような特徴があるとのことです。
- 20-30残基程度のドメインサイズが生成される
- 以下3種類のスキーマが典型的に生成される
- bundles of α-helices
- α-helix combined with β-strand
- β-strands connected by a hairpin turn
- αヘリックスの中心部で組み換えが起こると予想されることが多い
スキーマの解析から、イントロンの役割も考察することができます。どのDNA箇所も等しい頻度で遺伝子組み換えが起こると仮定すると、とあるイントロンが長いことは、その周辺のエキソン間で遺伝子組み換えが起こりやすいことを意味します。従って、そのエキソンは組み換えにより構造が破壊されない可能性が高いとのことです。この点において、本手法はタンパク質構造予測としてだけではなく、遺伝子の進化力学の解明にも役立つと、筆者らは主張しています。


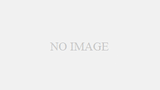
コメント