論文タイトル
Tertiary motifs as building blocks for the design of protein-binding peptides
出典
Protein Sci. 2022 Jun;31(6):e4322.

確認したいこと
- タンパク質のデザイン手法
要旨
「tertiary motifs(TERM)」を組み合わせることで、標的タンパク質に結合する分子をin silicoでデザインする手法を紹介しています。
解説など
TERMは、以前の記事でも紹介しました。
既存のデータベースから網羅的に分類された、タンパク質の部分的なモチーフのことです。
本論文では、標的タンパク質に結合する分子をデザインするために、このTERMを利用しています。
具体的には、まず標的タンパク質表面の広い範囲に対して、構造が相補的なTERMを網羅的に探索します。そして近接した位置に存在し得るTERMをつなぎ合わせることで、一つの結合タンパク質を構築していきます。
TERMを探索するライブラリは、PixelDBに由来しています。これには1,966種類の高品質のペプチド・タンパク質複合体が含まれています。
実際にシーズ(標的タンパク質に結合する候補TERMフラグメント)を生成すると、既知の天然構造も含まれている妥当な結果が得られていました。生成されたシーズには、その他に以下の特徴があったとのことです。
- 他の残基によって埋もれている界面は、マッチするシーズの数が少ない
- シーズにはαヘリックス、βシートが多く、コイル構造が少ない
このシーズを組み合わせるときには、「Fuser」と呼ばれる、プロトコルが使用されます。
この手法を用いて、主鎖骨格を構築しても、やはり天然のペプチドによる結合構造と類似した分子をデザインできていたとのことです。RMSDの高いポジションは、コイルやターンなどの2次構造を有する残基に対応していました。
この論文では、TRAF6というタンパク質に対して本手法を適用しています。しかしデザインされた分子に対して、ウェットな実験による評価はされておりませんでした。
本手法は、タンパク質表面に広い範囲で、形状相補性をもつ主鎖を構築することを重視しています。既往の深層学習を利用した手法は、デザインしたタンパク質の構造安定性は優れています。しかし結合親和性に重きをおいたデザインにおいては、形状相補的なデザイン、つまりドッキングの精度がなにより重要であるという主張です。これからも実施例が蓄積されることを期待しています。



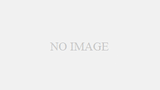
コメント