論文タイトル
Massively parallel de novo protein design for targeted therapeutics
出典
Nature. 2017 Oct 5;550(7674):74-79.
確認したいこと
引き続きBaker Labの論文です。
ミニプロテインライブラリを利用したde novo 結合タンパク質デザインの実施例を調査しました。
要旨
インフルエンザウイルスタンパク質(HA)とボツリヌス毒素タンパク質(BoNT)に対して結合する、低分子量のタンパク質のde novoデザインに成功したことを報告した論文です。
解説など
手法
本論文でデザインする分子は、40アミノ酸前後の非常に小さいタンパク質です。低分子量であるため必要な遺伝子の合成長も短く、また大腸菌でのタンパク調製が容易となります。
40アミノ酸で形作るタンパク質の骨格には、αヘリックスとβストランドが組み合わさったトポロジーを利用しています。αヘリックスをH、βストランドをEと示したとき、デザインする分子のトポロジーは以下の通りになります。
- HHH
- EHEE
- HEE
- EEHE
- HEEH
タンパクのデザインには、Rosettaを利用しています。
上記のトポロジーを有する分子を数千個デザインし、標的分子上にドッキング、その後結合界面のアミノ酸を最適化する流れです。スクリーニングは、過去に紹介した手法と同じく、酵母にデザインタンパク質を提示してFACSで結合分子をソーティングしています。
結果
スクリーニングで選抜された分子を大腸菌で発現し、結合を確認したり、結晶構造がモデリング構造と類似していることを示す流れはいつもの通りです。
HAとBoNTの2つの分子に対してデザインしていますが、それぞれの標的分子に対して適するトポロジーの傾向は異なっていたとのことです。この結果は、単一のバックボーンからではデザインの成功率が下がることを意味しますので、重要な知見といえます。
高い結合活性を示す分子は、シミュレーションされたフォールディングエネルギーや結合エネルギーの値が低かったことが示されています。また結合活性は、モデリングの精度やinterfaceに関与する残基数とも、正の相関があったとのことです。
ちなみに、デザインされたタンパク質は免疫原性も低かったそうです。



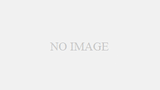
コメント